| 森川造園 | 有限会社 森川造園 サイトマップ |
| 倉敷市児島赤崎3-2-59 Tel 086-472-3741 Fax 086-472-1741 | お問い合わせ |
和風庭園|つくばい(蹲)・石灯篭
つくばい(蹲)・石灯篭
 |
和風庭園の景色として、 このページでは、
|
つくばい(蹲)名の由来
つくばい(蹲)とは、もともと茶道の習わしで、
お客様が這いつくばるように、 身を低くして手を清めたことが始まりです。
しかし、現在では、演出として用いられることも、多くなりました。
つくばい(蹲)は、茶事の際、席入りする前に、手水を使って心身を清めるもので、
露地には欠くことのできないものです。
つくばい(蹲)の構成
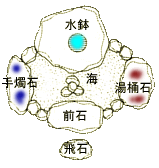 つくばい(蹲)は、水鉢を中心に、手水を使うために乗る前石、夜の茶会時に手燭を置くための手燭石、寒中に暖かい湯の入った桶を出すための湯桶石、3つの役石で構成されています。
つくばい(蹲)は、水鉢を中心に、手水を使うために乗る前石、夜の茶会時に手燭を置くための手燭石、寒中に暖かい湯の入った桶を出すための湯桶石、3つの役石で構成されています。
手燭石と湯桶石の左右は、茶道の流派によって異なります。
これらの役石に囲まれた部分は海と呼ばれています。
水鉢からこぼれる水を、受けるために低くし、砂利やゴロタ石などを敷きつめます。
灯篭の始まり
灯篭は庭園とはまるで関係なく、仏にささげる明かり、すなわち献灯として発祥したそうです。
飛鳥時代に、仏教とともに中国から伝えられたと、考えられています。
灯篭と千利休
石灯篭が、庭園と関係を持つようになったきっかけは、桃山時代です。
この頃に始まった茶庭(路地)の照明として、茶人達が古い灯篭に目をつけ利用したのが初めと考えられます。
一説には、千利休が最初だといわれています。
このように灯篭は実用目的から利用されましたが、それは景としても非常に美しかったので、以後その風情が愛され、茶庭以外の庭にも導入されました。
 |
 |
 |
 |
| 和風庭園の景色施工例 |
有限会社 森川造園 倉敷市児島赤崎3-2-59
|